前回に引き続き、10個目の輔行訣のバージョンの日本語意訳を覚え書きとしてここに記す。全12バージョンある。
十. 『輔行訣』張偓南別集本 (1980年6月)
この文献は、縦18.1cm、横10.6cmほどの大きさで、毛筆で縦書きされています。表紙を含めてわずか12ページです。各ページには7〜9行、1行あたり約15字で書かれています。表紙の左側には『陶弘景先生五臓法要別集』と書かれており、右側には「五大補湯、五労方五首、丸薬方二首」などの内容の要約が記されています。
本の冒頭には、張大昌氏による題記があります。
「これらの処方は、元々私の先祖である偓南先生の別写本の中に保存されていたものである。しかし『文化大革命』の際、すべて燃えてしまった。その後、古紙の山の中から、私が若い頃に写した写本を一部見つけ、急いでこの一冊を書き写した。これにより、広陵散(※1)が世に埋もれるのを免れた。1980年6月、威県(※2)の張唯静が記す。年老いて目がかすんでいるため、毛筆で書いたものの、まるで落書きのようで、三度もため息をつかずにはいられない。良い書物を作ることができなかった。」
(※1)広陵散:古代中国の琴の曲。戦国時代の竹林の七賢の一人、稽康が処刑される際にこの曲を弾き、この曲が二度と世に伝わらなくなってしまうことを嘆いたという故事から、滅びてしまった物事を惜しむ意味で使われる。
(※2)威県:現在の河北省邢台市威県。
(この題記は、張大昌氏が毛筆で書き写し終えた後、万年筆で追記したものと推測されます。)
この写本の最後に添付されている「建中甘草丸」(『外台秘要』巻十七「長肌膚方三首」の三「甘草丸」P478、元は『延年方』第1巻から)と「大香丸」(『外台秘要』巻九「積年久咳方二十一首」の四「香豉丸」P263〜264、元は『深師方』第18巻から)は、もともとの『輔行訣』には含まれていないものです。
この写本には、「1980年6月 張唯静が書き写す、当時56歳」と記されています。張大昌氏はこの写本を書き写した後、弟子である衣之鏢氏に厳重に保管するよう託しました。その後、この写本は複数回コピーされました。
この文献は、張大昌氏が1980年6月に、彼の祖父である張偓南氏の医方を改めて書き写したものであるため、「別集本」と呼ばれています。この本自体は1980年に書き写されたものですが、その元となった原本は1966年から1978年の間に発見されました。その源をたどると、張偓南氏が敦煌(※3)でこの書物を手に入れた1918年から、彼が亡くなる1919年の間、あるいは敦煌で夜中に書き写した写本そのものと関係があると考えられます。
コメント:「建中甘草丸」、「大香丸」は引用中医である。ただ、外台秘要も結構経方しているので、引用しても臨床力の上では影響ない。


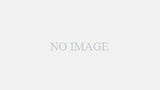

コメント